■画像処理基本特許と発明王レメルソン
 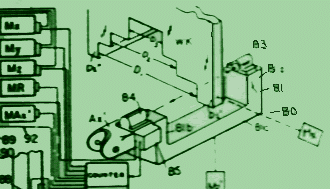
発明王レメルソン レメルソンが1954年に特許を申請した万能ロボットの図面の
特許収入で5億ドルを稼ぐ。 一部。測定ヘッド(81)で光を発し製造物をスキャンして測定する。
この測定値はコンピュータにより処理される。
発明王レメルソンが画像処理基本特許を取得し日本に攻勢!
画像処理にも次のような基本特許があるのをご存じだろうか?
「イメージセンサで映像をとりこみデジタル化しコンピュータで処理する」
■そもそも基本特許とはなにか?
装置、システムまたは処理方法を構築する基本的な特許であり、これを用いた製品、
商品を製造、販売する場合には特許権利者へのロイヤリティ(特許権料)を支払う
必要がある。
「画像処理」にも基本特許が成立したという事は、画像処理応用製品にもロイヤリ
ティの問題がでてきたという事になる。
■なぜ今頃画像処理の基本特許なのか?
といっても読者のみなさんは不思議に思うかもしれない。なぜなら上記画像処理の
概念はコンピュータが登場して間もなく、1950年代前半には確立されていたか
らである。通常日本では、発明の出願から20年までを特許権の有効期間としてお
り、1990年代にまでそれが適用されるとはいかなる事なのか?
そしてそもそもこの基本特許を所有している人物とは何者なのか?
そしてそのロイヤリティとは?
■発明王レメルソン
かの発明王エジソンに迫る500件近くの特許を取得し、そのロイヤリティで数億ド
ルを稼いだ人物が米国にいる。
コーンフレークの箱を開ける時に引っ張るあのギザギザの開封用の紙は氏の初期の特
許であるが、今や特許取得件数と特許収入の双方で世界一となった。
その氏が1950年代初頭に、画像処理の基本となる「アイデア」を出願していたの
である。
■再度問う!なぜ今頃画像処理の基本特許なのか?
このあまりにも古い「アイデア」は長く米国の特許庁で眠っていた(正確には眠りな
がら細胞分裂を繰り返し、その延命を計ってきた。それを許した米国特許庁の手続き
に問題があったという見方もある)が1980年代も終わろうとする時に、急に息を
吹き返した。そして同じ頃、米国の関税法337条と特許法271条が改正された。
その結果、日本国内の画像処理手段を用いて製造された製品が米国に輸出された場合、
この「画像処理」基本特許の適用対象となる様になったのである。そのロイヤリティ
も非常識な額(数百億円)にのぼる。
■危機に立つ世界の画像処理関連産業!
1989年秋、氏からの最初の警告書を日本のメーカー数社が受け取った時、その途
方もないロイヤリティの請求に愕然とした(製品原価の6%を支払えという内容)。
そもそも何でこの過去の遺物がよみがえったのか?米国の特許庁の手続きに問題はな
いのか?そしてこの「アイデア」は本当に基本特許に値するのか?画像処理研究者、
知的財産権担当者の眠れない日々が始まった。小生も当時この問題に関わった一人で
あったが、基本特許に値する特許とはどうにも思えなかった。
そして1992年7月、数ケ月前の最後通告に続き、日本の自動車メーカー4社が提
訴された。正しい分析をするだけの時間は許されていなかった。この後、4社を含む
自動車メーカー12社、一部の大手電機メーカーらは1ケ月の間に合わせて1億ドル
を支払った。選んだのは係争ではなく和解という選択肢であった。
氏はここで得た資金を元手に、さらにモトローラなど多くの企業を訴訟に巻き込み9
4年までに5億ドルのライセンス料を得た。どんどん膨張する発明王の特許権行使の
パワー。現在レメルソンと画像処理に関する熾烈な特許訴訟を展開中のフォード社の
弁護士は憤りを込めて次のように語る。「特許出願後何十年も経って新技術をカバー
するよう操作された氏の特許が水面に顔を出した」。
※参考資料 THE WALL STREET JOURNAL(1997/4/9より)
発明王レメルソン本年10月1日逝く!
■特許権は氏の特許訴訟会社が引き継ぐ!
500件の特許を取得し、自らエジソンの再来と自称した発明王レメルソンが逝っ
た。74才であった。近年では、画像処理の基本特許を始め、バーコードやマウス
などの特許も保有し、特に世界有数の超大手企業を相手に特許訴訟を繰り返し、巨
万の富を築き上げてきた。その故に、米国内に「特許権は訴訟のためのものか」と
いう論議を巻き起こしてきた。フォード社等、真っ向から氏と対決してきた幾多の
企業はひとまず安堵というところであろう。しかし、氏の特許権は氏の一族が関与
する会社が引き継ぐことになり、現在係争中の特許についてはなお予断を許さない
であろう。
※参考資料 THE NEWYORK TIMES(1997/10/2より)
|